News / Report
【インタビューコラム】組織の多様化が多様性への入口 〜松中権代表に聞いた、イギリスと日本のLGBTQ〜

=========
LGBTQの人々の平等と権利確保を進めるイギリス。今年3月初旬、プライドハウス東京の松中権代表は、駐日英国大使館のオファーを受けロンドンへ飛んだ。現地のNGO、メディア、政府関係者と会い、松中代表はイギリスの「今」をどう読み取り、日本社会とどう対比させたのか。コロナ禍でも活動の歩みを止めることなく、10月11日に日本初となる常設の総合LGBTQセンター「プライドハウス東京レガシー(東京都新宿区)」をオープンした直後の松中代表に、ロンドン渡航を改めて振り返ってもらい、また新型コロナウイルスが及ぼす多様性への影響や今後の展望についても語ってもらった。
(聞き手・駐日英国大使館政治部 浅川聖)
=========
3月7-12日の日程でロンドンへ渡航頂きありがとうございました。到着後先ず、LGBTQを支援するNGOとしてはイギリス最大の「ストーンウォール(Stonewall)」でスポーツ部署のディレクターを務めるサントスさん(Robbie de Santos)とオンライン面談をされました。具体的に、どのようなお話を聞かれましたか?
オリンピック・パラリンピックが東京で開催されることから、スポーツとLGBTQの関係が課題だと考えていると話したところ、サントスさんから「シューレース(靴紐)プロジェクト(※1)」を紹介されました。ストーンウォールは、発信力の強いアスリートの協力を得て、アスリート同士の横のパイプを活用しながらこのプロジェクトを進めているようでした。公にカミングアウトしたアスリートには、SNSなどを通じて全く知らない選手から直接相談が寄せられることも結構あるらしく、表に出てはいない選手同士の繋がりも蓄積されていると伺いました。また、こういった繋がりを使って、スポーツ選手が抱える問題などのヒアリングにも積極的でした。
これに一部関わるのですが、ストーンウォール独自でLGBTQとスポーツに係る調査を行い、データに裏付けられた説得力のあるプロジェクトの実施を目指していると言っていました。そして、プロジェクトを更に進めるフック(きっかけ)となったのは、資金力と発信力で影響力のある企業の参加を受けたことにあったようです。私が代表を務めるプライドハウス東京も、選手と企業へリーチする上で同じような経験をしてきたので、進むべき道は間違っていないと思った一方、サントスさんとの話をとおして、イギリスでは、選手、業界団体、企業が本気で動いている印象を受けました。
ロンドンでのヒントもあり、プライドハウス東京の参画企業のひとつであるアシックスさんと一緒に「レインボーシューレス」を制作することとしました。アスリート発信チームや祝祭・スポーツ医イベント・ボランティアチームと連携し、スポーツ関係者や指導者、イベント参加者にも輪を拡げていければと思っています。(※11月1日〜8日にて開催された、オンラインレインボーマラソン2020 の参加者に配布されました。)
(※1 選手がレインボーカラーの靴紐を結び、スポーツが性的指向や性自認に関わらず誰にでも開かれたものであるとの連帯を示す活動。なおストーンウォールによれば、LGBTQの人々の43%は、公のスポーツイベントに歓迎されているとは感じていないと報告されている。)
 The Global Equality Caucus
The Global Equality Caucus
Alan Wardle氏
Stonewall Sports Ambassador
Amazin LeThi氏
―――なぜイギリスでは、民間企業がLGBTQの課題に本気なのでしょうか?
イギリスだけではない欧米の特徴だと思いますが、それぞれの企業が、企業間の競争というよりも社会や従業員からどう見られているかを基準に物事を決めているからではないでしょうか。あくまで経験則ですが、日本企業はどちらかと言うと横並びのカルチャー。LGBTQのことも「あの企業がやっているからうちもやろう」というマインドで動いている場合が多いと感じます。
欧米の企業活動は、従業員や顧客の満足度を高めるためにLGBTQを含めた色々な活動が経営に資するという考えが根底にあると思います。その背景には、欧米で、LGBTQに対するネガティブな発信や行動にかかわった企業に対する不買運動がいち早く起こり、LGBTQに取り組んでいないことが逆にリスクになった経験が関係しているからかもしれません。欧米の企業は、LGBTQや多様性のことを、社会の構成員である企業市民として、社会貢献やボランティアという呈で進めるのではなく、より良い職場づくりを行い、社会づくりに貢献することで「企業価値」を高めていくことを、大きな目的に置いていると捉えています。
―――滞在中、複数のメディア関係者にもお会いになられましたが、イギリスのLGBTQや多様性に関わる取り組みを発信するメディア側の姿勢に関して、何か日本と違う発見はありましたか?
イギリスのテレビ局であるITVでダイバーシティー部署のディレクターを務めるアディ・ロウクリフ(Ade Rawcliffe(※2))さんの話は印象的でした。ロウクリフさんとは昨年、NHKが主催した世界の教育番組を紹介する「Japan Prize 2019」というイベントでご一緒していたので、今回ロンドンで再会でき嬉しかったです。
そもそも、ITVには、ダイバーシティー&インクルージョン(D&I:多様性&包摂性)を預かる部署がきちん構えられています。これだけで、ITVというTV局はD&Iをきちんとコアに考えるメディアなんだなということが伝わってきますし、実際、全ての番組が世に出る前に、このダイバーシティー部署のフィルターを通らなくてはなりません。ロウクリフさんは、D&Iを進める理由について、視聴者が多様なのだから番組の内容も多様性に富んだものでなくてはならないというシンプルな考えがあると話されていました。確かにそうなのですが、発信側であるITVには、組織体にも、番組作成のプロセスにも、具体的な番組の内容にも、「多様であること」が全てに組み込まれているので、改めて素晴らしいと思いました。
(※2 ロウクリフさんは、2012年のロンドン五輪ではMeet the Superhumans、2016年のリオ五輪ではWe are the Superhumans:Yes I canという、どちらもパラリンピックの視聴促進に貢献したキャンペーン動画の制作に深く携わった)
 iTV
iTV
Ade Rawcliffe氏とMatt Scarff氏
―――視聴者が多様なのだから多様な番組を作る。日本では少し難しいような気もしますが?
私も最初はそう考えていました。けれど、ITVの体制を聞いた後、これは視聴者側の問題ではないのかもしれないと思い始めました。これまた経験則の話ですが、日本のメディアは、凄く体育会系で男社会です。特に意思決定の出来る上層部になればなるほど男性中心。そうすると、例えば、大物演者と直接話せるのはそういった組織内の男性中心の上層部のみとなり、現場の若手が「この表現は大丈夫なのか…」と思っても中々番組構成に反映されづらくなる。警鐘を鳴らせるプロセスが乏しいからです。要するに、視聴者が多様であるか否かよりも、発信する側の構造を変えることが重要であり、これこそ、日本でD&Iが十分反映されづらい理由ではないかと思います。
―――ロウクリフさんは、多様性を巡るイギリスメディアの課題について何か話されていましたか?
そうですね、D&I推進は一つのテレビ局がやってもしょうがないと言われていて、恐らくこれが課題でしょうか。メディア同士の横の繋がりをどうするかという問題。そのため、ロウクリフさんは、D&Iに関するガイドラインをオープンコンテンツとして用意して、それを横断的に同業他社に共有しながら業界自体の底上げをする取り組みをしていると話していました。
それと、昨年お会いした時の話なのですが、その際番組制作をする上で心掛けている点などを議論されていました。先ず、話されていたのは、マイノリティをかわいそうな人、壁にぶつかっている人、という側面から焦点を当てても視聴者の心は動かしにくいということ。むしろ、その人物が何かを勝ち取る姿や、その人物を応援する周囲の反応や気持ちを撮った方が視聴者の共感を呼び易いと言っていました。世の中の人はネガティブな事よりもポジティブな部分に共感したいと思っているようです。
次に話されていたのは、インターセクショナリティー(Intersectionality)という、例えばLGBTQの一人であり、且つ癌克服者でもあったりする等、一人の人間の中には、幾つもの多層性が存在するという視点です。この視点からロウクリフさんは、切り口を変えることで、LGBTQの人々も全然違って見えたりするかもしれないと話していました。現状、メディアがそこまで追うのは難しいけれど、実は、別の切り口から見たその人の方がリアルだったりするかもしれないよね、とも発言されていましたね。
最後に、D&Iのコアな部分として、ロウクリフさんは、「Dの部分はみんなが違うということしか言っていない」と述べつつ、Iの方を重視していると強調されていたことに凄く共感しました。私は、思考停止ワードだと思うので、みんな違ってみんな良い、という言葉が凄く嫌いです。これを印籠の様に使う人もいるけど、人は、違うからぶつかる。けれど、一緒に働いて生活をしていかなければならないですよね。私は、どうやって互いを包摂(インクルード)していくか、ロウクリフさんが示唆されたように、そのプロセスの方がより重要だと思っています。
―――日程の最後には、英国外務・連邦省を訪問頂き、エレイン・チャド国際人権課LGBT担当とエミリー・メタン東アジア太平洋課日本担当にお会い頂きました。
開口一番、チャドさんから、日本政府にも「平等な権利のための連合:(ERC)Equal Rights Coalition(※3)」に参加して欲しいがどうしたら良いか? と尋ねられました。
私は、ERCの様な国際的なグループに関心を持つとなると、やっぱりそこと近いのは、政治や行政になると思っています。けれど、日本はそこに多様性がない。だから日本は、この分野で国際的な動きに合わせるのが難しくなっているのではないでしょうか。
多様性は既に当たり前で、LGBTQはすぐ隣に居る人であったりします。けれど、そのことに気が付いていなかったり、そこに課題があることを意識していない場合が多く、結局それを感じやすいのは、若い世代や女性だったりする。これは、日本がまだまだ男性中心の社会だからです。そのため、この男性層がアンテナを立てて、LGBTQが居る事に気がついて貰わないと、多様性の入口が生まれず、中々日本社会に入っていかないのだと思います。
そして、最後に判断するのは多数決という方法ですから、この土壌にマイノリティや当事者が居ないとどうしても声は漏れてしまう。組織の多様性を確保するのはとても大事です。
(※3 LGBTIの人々の人権確保を目指す国際的な政府間組織。現在イギリスはアルゼンチンと共に共同委員長を務めている。世界42か国が加盟。日本は未加盟。)
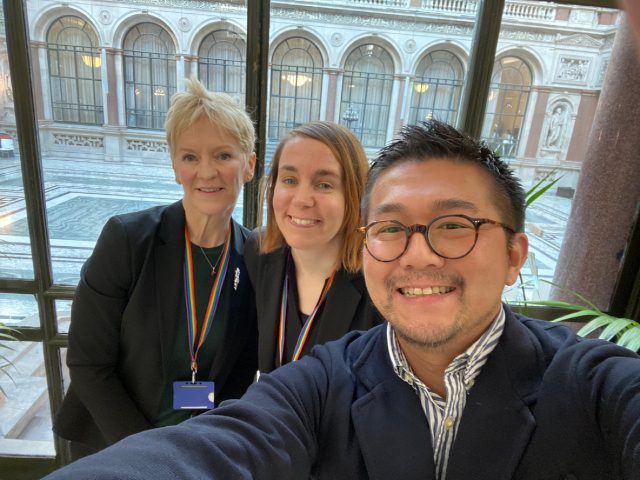 英国外務省
英国外務省
エレイン・チャド氏とエミリー・メタン氏
―――最後に、コロナが与える多様性への影響、そしてロンドン渡航を踏まえた松中さんの今後について教えていただけますか?
コロナのLGBTQへの影響ですが、コミュニケーションがよりオンライン化されたことで東京以外のLGBTQの存在が可視化されました。毎年ゴールデンウィーク中に代々木公園で開催されていた「東京レインボープライド」もそうですが、LGBTQ関係は、東京中心で大きく動くムーブメントになりがちであることは否めませんでした。もちろんこれまでも、様々な企画が、ゆくゆくは地方でもやりましょうと言っていましたが、正直、東京中心で進むことをどこか何か言い訳の様に繰り返してきた。けれど、今後オフラインになったとしても、コロナでLGBTQの存在がリアルになったため、東京以外のエリアに対しても意識的になり、置いていかれにくくなるのではないでしょうか。工夫すれば繋がることは出来るよね、距離は越えられるよね、となりました。実は、ストーンウォールのサントスさんと話した時にも同じような話をしたのです。当時はコロナがここまで大きくなるとは思っていませんでしたが、ZOOM会議は、顔出ししなくて良いから匿名性も確保される。サントスさんは、オンラインはオプションとしてではなく、使える物として出てきたと話していました。
二つ目の影響は、危機的な状況だからこそ、色々なセーフティーネットからあぶれてしまう人が出てきたことです。同性パートナーが家族として扱われるのかという不安、濃厚接触者とされたら行動範囲を示さないとならない、コロナと同じ感染症課で診られるHIV患者は自分のことがばれる可能性が高くなった。コロナは皆が平等に経験している危機なのですが、実は、二重に危機を感じているのはマイノリティの人たちです。
最後に、今後の活動ですが、日本のLGBTQカルチャーをアーカイブ化できたらなと思っています。これは、コロナを受けて余計に感じる様になりました。私は「Save the二丁目」という新宿二丁目に関する活動にも関わっていましたが、小さなお店も多く3密空間なのでお店がどんどん閉まっています。けれど、二丁目は、あの空間に数百件のお店が並んでいるからあのような街となり、そこで救われている人もいる。昔の歴史や学びが今後役に立つかもしれないけど、日本では、LGBTQカルチャーをあまり保存してきませんでした。ロンドンには、ミュージアムを作りLGBTQの歴史を残す「クイア・ブリテン」というプロジェクトベースで活動する人たちいます。今後、そこでのノウハウも参考にしながら、LGBTQカルチャーのアーカイブ化を日本でも進めたいと思っています。
ーーーインタビューを終えて
貴重な一片を切り取って来て頂いた。もちろんLGBTQに関する現地イギリスの一風景をだ。
松中代表へのインタビューを終えて、LGBTQの課題の一つは、社会の多様性への要求という需要側だけでなく、それを発信・推進する供給側にも多様性が求められている現実であると感じた。松中代表が見たロンドンは、そんな視点を再認識させた現場だったかもしれない。
コロナが世の中を飲み込み、私が松中代表と対面でお話ししたのは、ロンドン渡航からしばらく経った11月初旬。オープンしたてのプライドハウス東京レガシーにお邪魔した時であった。「まだまだ手探り状態ですよ」と恐縮する松中代表とスタッフであったが、数百冊にも及ぶLGBTQ関連のライブラリーコーナーには、専門書から各国大使館が寄贈した絵本まで取り揃えられ、コロナ禍でも可能な限り歩み続けていた事が看取できた。スタッフの一人は、ここをLGBTQに関わる全ての人が行き来する「中心地(ハブ)」にしたいと話し、一緒に行った私の同僚は「心地良い空間だったね」と帰り道につぶやいていた。
ロンドン渡航で松中代表が得た学びや価値観がプライドハウス東京レガシーを媒介し、ここ東京で活かされていくことを強く願う。松中代表と久しぶりにお会いし、その願いは既に現場に還元されていたのであるが。
 Sports Media LGBT+
Sports Media LGBT+
Jon Holmes氏
 プライドハウス・インターナショナル
プライドハウス・インターナショナル
Lou Englefield氏とHugh Torrance氏
 Thomson Reuter Foundation
Thomson Reuter Foundation
Rachel Savage氏
 The Kaleidoscope Trust
The Kaleidoscope Trust
Jesse Sperling氏とJuan Miguel Sanchez Marin氏
 Gay Games
Gay Games
Leviathen Hendricks氏
関連
ニュース/
レポート
-
レポート

國學院大學久我山高等学校・女子部~オルガノン株式会社さまと協働プロジェクトを実施 ~多様性を尊重し、共生社会を目指すために
協賛企業のオルガノン株式会社さまのご協力を得て、國學院大學久我山高等学校・女子部で出張授業を実施しました。 当日はオルガノン株式会社の代表取締役社長アルパ アルプテキン様、ボランティ...
-
レポート

【アライアスリート・インタビュー③】男でも女でもない、ただ「齊藤夕眞」として。 Qを公表したサッカー選手が歩んだ自分らしさへの道のり
プライドハウス東京(PHT)では、2022年より、「アライアスリート」の輪を広げる活動に取り組んでいます。アライ(ally)とは、「同盟、味方」などを表す言葉。LGBTQ+当事者の味方としてともに...
-
レポート

【アライアスリート・インタビュー①】スポーツの力で、誰もが自分らしい居場所を持てる社会に。元ラグビー日本代表・鈴木彩香の想い
プライドハウス東京(PHT)では、2022年より、「アライアスリート」の輪を広げる活動に取り組んでいます。アライ(ally)とは、「同盟、味方」などを表す言葉。LGBTQ+当事者の味方としてともに...

